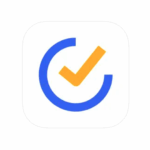目次
[開く]「今日のランチ、何食べた?」――そんな会話が、近い将来「どのデータをダウンロードして食べた?」に変わるかもしれません。
「グルメテーブルかけ」のようなドラえもんのひみつ道具が、ついに現実のものになろうとしています。
コンピューターが生み出した「仮想の食べ物」を、実際に舌で味わえる。
そんな驚きのテクノロジーが、アメリカの研究者たちによって開発されました。
VRゴーグルをかけると目の前に現れる、おいしそうな料理。
それを食べたつもりになると、なんと本当に味がするというのです!
その秘密は「電気味覚」と呼ばれる技術。
専用の装置についた電極を舌に当てることで、電気の力でしょっぱさや甘さ、酸っぱさといった基本的な味覚を直接脳に届ける仕組みです。
実際に30人で行われた実験では、被験者たちは仮想空間のジュースが「甘い」か「しょっぱい」かを、高い精度で当てられたというから驚きですね。
この技術が発展すれば、健康のために塩分や糖分を控えている人が、味気ない食事を「いつもの味」で楽しめたり、ネットショッピングで高級食材を「味見」してから買えたりする未来がやってきます。
メタバースで友達と集まって、見たこともない架空のフルーツを味わう、なんてことも夢ではありません。
今回は、そんな驚きのテクノロジーをきっかけに、「食と五感」にまつわる面白い雑学を深掘りしてお届けします。
あなたの食事がもっと楽しくなること間違いなし!
【知ってた?】食事が10倍面白くなる!味覚とテクノロジーの雑学
電気で味を作り出すなんて、まさにSFの世界ですよね。
しかし、私たちの「食」と「五感」の関係は、最新技術だけでなく、日常生活の中にも不思議で面白い発見が隠されています。
ここからは、味覚をさらに深掘りし、あなたの食生活を豊かにする雑学をご紹介します!
雑学①:味は舌だけで感じているワケじゃない!「音」で変わるポテチの食感
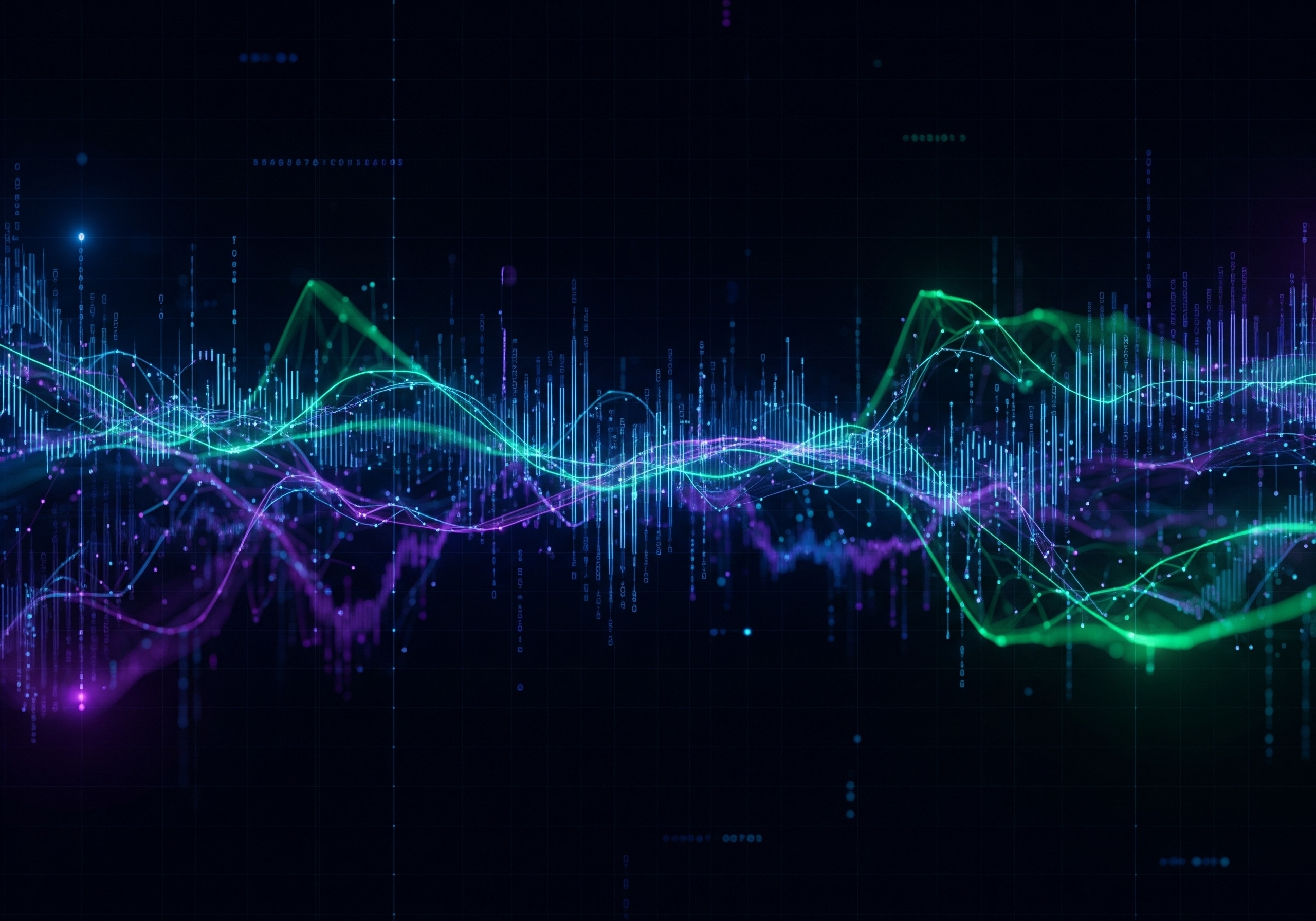
「味は舌で感じるもの」と、私たちは当たり前のように思っています。
しかし、実は脳は、視覚、嗅覚、聴覚、触覚といった他の五感からの情報を総動員して「味」を判断しているのです。
これを専門的には「クロスモーダル現象」と呼びます。
その最も有名な例が、「ポテトチップスの音」に関する実験。
イギリスのオックスフォード大学の研究で、被験者にヘッドフォンをつけてポテトチップスを食べてもらい、聞こえる咀嚼音(そしゃくおん)を大きくしたり、周波数を変えたりしました。
すると、驚くべきことに、咀嚼音が大きいほど「より新鮮で、よりパリパリしている」と感じることが分かったのです。食べているポテチは全く同じものなのに、です!
この他にも、
- 赤い色の飲み物は、他の色の飲み物より甘く感じる
- 重い食器で食べると、同じヨーグルトでも高級で密度が濃く感じる
といった研究報告があります。
レストランで流れる音楽や、食器の色・形も、実は料理の味を左右する重要な要素だったのですね。
出典:
- Eating with our eyes: From visual hunger to digital satiation – Brain and Cognition: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28837902/
雑学②:日本発の変態的(!?)技術!「味わうテレビ」から「味を強くするお椀」まで

実は、冒頭で紹介した「電気味覚」の研究は、日本が世界をリードする分野の一つ。
その第一人者が、明治大学の宮下芳明教授です。
宮下教授が開発して世界を驚かせたのが、画面を舐めるとその映像の味がする「味わうテレビ(Taste the TV)」。
テレビ画面に10種類の味の液体を吹き付けてブレンドし、食べ物の味を再現するという、まさに驚きの発明ですね。
そして、この技術はすでに私たちの生活に近づいています。
飲料メーカーのキリンホールディングスは、宮下研究室と共同で、**微弱な電流で塩味やうま味を約1.5倍に増強させる食器「エレキソルト」**を開発。
2024年には数量限定で抽選販売も行われ、大きな話題を呼びました。
これを使えば、塩分を大幅にカットしたお味噌汁でも、まるで普通のお味噌汁のようにしっかりとした味を感じることができるのです。
健康上の理由で減塩が必要な方にとって、これはまさに救世主のような技術。
日本の「もったいない」精神や「おもてなし」の心が、こんな未来の食文化を生み出しているのかもしれません。
出典:
- 明治大学 宮下研究室: https://miyashita.com/
- キリンホールディングス | 世界初!塩味を約1.5倍に増強させるスプーン・お椀を製品化 「エレキソルト」: https://electricsalt.kirin.co.jp/
雑学③:未来の食事はダウンロードする時代へ?VR・ARが変える食生活

冒頭でご紹介したような仮想味覚技術の応用範囲は無限大です。
- 医療・介護分野: 食欲が湧かない患者さんや高齢者の方に、栄養価の高い流動食を「ステーキの味」として楽しんでもらう。
- 宇宙開発: 長期滞在する宇宙飛行士が、故郷の味をVRで楽しむことで、精神的なストレスを和らげる。
- エンターテイメント: メタバース空間のアバターが、友人たちと仮想レストランで食事会。現実の自分も、その料理の味をリアルタイムで体験する。
さらに、この技術は「食のバリアフリー」も実現するかもしれません。
アレルギーで特定のものが食べられない子供が、その味だけでも安全に体験できたり、高価でなかなか手が出ない高級食材の味を気軽に試したり…。
食は、単に栄養を摂取するだけの行為ではありません。
人と人とのコミュニケーションを円滑にし、文化を育み、人生を豊かにする大切な要素です。
「仮想の食」が「現実の食」を補い、拡張することで、私たちの食生活は、もっと自由で、もっと創造的なものへと進化していくことでしょう。
食卓から宇宙まで、テクノロジーが変える「味」の未来。
次はどんな驚きのニュースが飛び込んでくるのか、今から楽しみでなりませんね!
テクノロジーは「食」をエンターテイメントに変える
「電気で味を作る」という驚きのニュースから始まった今回の食レポ。
しかし、掘り下げてみると、その根底には「味は脳で感じる総合芸術である」という、シンプルながらも奥深い事実がありました。
ポテトチップスの音、食器の重さ、そして料理の色。
私たちの脳は、舌から送られる信号だけでなく、目や耳、手から入ってくる情報を巧みにブレンドして、日々の食事の「おいしさ」を演出してくれているのです。
そして今、その不思議な脳の仕組みをハックし、食をより豊かにしようとするテクノロジーが、日本をはじめ世界中で生まれています。
それは、単に珍しいだけの技術ではありません。
減塩食をおいしくしたり、アレルギーの壁を越えさせたりと、多くの人を幸せにする可能性を秘めた、心温かいイノベーションなのです。
「食」という、私たちにとって最も身近で根源的なテーマが、テクノロジーと出会うことで、無限の可能性を秘めたフロンティアに変わろうとしています。
次の食事では、あなたもぜひ、五感をフル活用して「脳が感じる味」をじっくりと楽しんでみてはいかがでしょうか。
【記事執筆の元となった海外記事】
SciTechDaily “Virtual Food Is Here – And You Can Actually Taste It!”: https://scitechdaily.com/virtual-food-is-here-and-you-can-actually-taste-it/